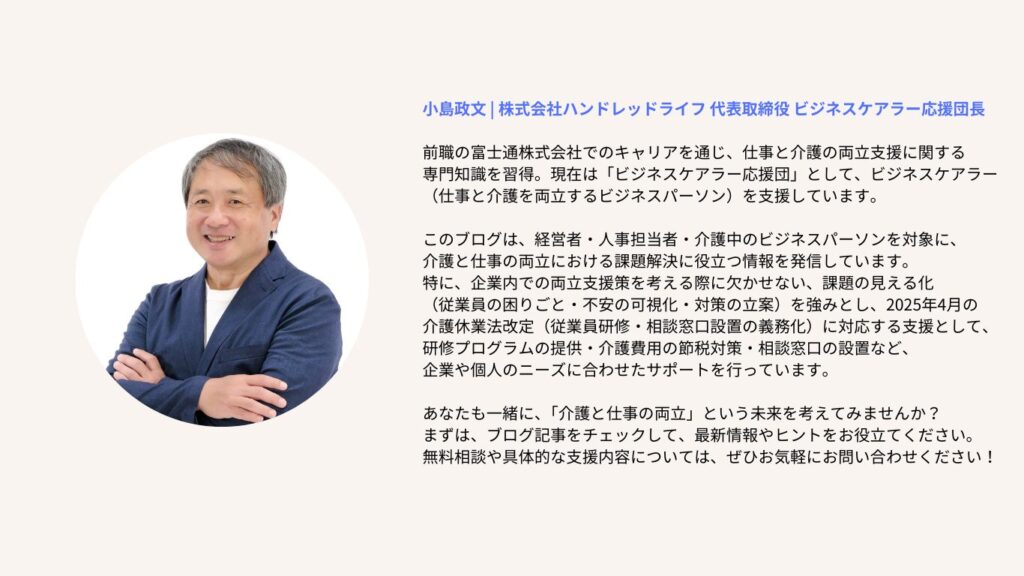介護と仕事の両立に悩む“ビジネスケアラー”の支援を目的とした制度整備が進む一方で、「従業員の介護実態把握ができていない」と課題を感じている企業は少なくありません。ビジネスケアラーは表面化しにくく、支援が必要な社員を見逃してしまうケースもあります。「この記事では、ビジネスケアラーサポートを効果的に進めるうえで不可欠な介護実態の把握について、調査方法・活用ツール・成功事例などを具体的に解説します。」
目次
1. なぜビジネスケアラーの介護実態は把握しにくいのか?

1-1 表面化しない“ビジネスケアラー”という存在
多くの社員は介護をしていることを周囲に打ち明けず、限界を迎えて初めて会社が把握するケースが多々あります。プライバシーの問題やキャリアへの不安が、申告をためらわせる要因です。
1-2 ビジネスケアラーサポートが形骸化するリスク
「ビジネスケアラーサポート」は制度だけ整えても、対象者を把握できなければ効果は限定的です。従業員の介護実態把握ができていないと、制度利用者が増えず、離職防止にもつながりません。
2. ビジネスケアラー実態を把握するための調査の基本
2-1 ビジネスケアラーの介護実態を把握する調査の目的とメリット
実態調査は、社員の介護状況を可視化し、支援が必要な層を把握する第一歩です。人事部門が状況を理解することで、制度設計や個別支援がしやすくなります。
2-2 アンケート設計のポイントと注意点
「家族に要介護者はいるか」「将来、家族に要介護になりそうな人がいるか」「介護にかける時間」「介護における課題」など、匿名性を担保しつつ具体的な状況を把握する設問設計が重要です。
3. 実態把握に役立つビジネスケアラーサポートの施策
3-1 定期的なヒアリングとアンケートの併用
年1回の全社アンケートに加え、管理職との面談などの非公式な場でも情報収集を行いましょう。ヒアリングで「ビジネスケアラーサポート」の必要性を再認識する機会になります。「実態把握の精度向上は、働き方改革やエンゲージメント向上にも直結します。従業員の心理的負担を軽減し、介護離職の抑制にも寄与することが分かっています。」
3-2 相談窓口の設置と周知の徹底
実態把握には、安心して相談できる環境の整備も不可欠です。匿名相談や社外相談窓口の設置により、社員が声を上げやすくなります。
4. 実態把握を踏まえた支援制度の設計ポイント
4-1 実態に即したビジネスケアラー支援制度の設計例
「ビジネスケアラーサポート 従業員の介護実態把握ができていない」状態を改善した後、重要になるのが“実態に即した支援制度の設計”です。介護にかかる時間帯・頻度・期間などの実態を基に、制度内容を柔軟に設計する必要があります。
たとえば、短時間勤務制度は「午前だけ」「午後だけ」といった選択肢を設けることで利用しやすくなります。また、介護相談窓口を人事だけでなく外部にも設置することで、社員の心理的ハードルを下げる工夫も有効です。
さらに、要介護度別に利用可能な支援内容を整理しておくことで、本人が自分に合った制度を把握しやすくなるなど、制度を「使われるもの」に進化させる視点が求められます。
4-2 管理職研修を通じた“気づき”の促進
「従業員の介護実態把握ができていない」状態を脱するため、管理職向けにビジネスケアラー支援研修を実施。気づきと声かけの重要性を浸透させることで、介護のサインを見逃さない体制を構築しました。
5. ビジネスケアラーサポート強化に向けた今後のアクション
5-1 人的資本情報開示との連動も視野に
「調査結果は、人的資本経営の文脈でも有効です。人的資本開示制度において、“従業員の介護支援”が情報開示の評価要素に含まれるケースも増えています。」
5-2 ビジネスケアラーサポートを強化する継続的な介護実態把握体制の構築
一度の調査で終わらせず、PDCAを回しながら継続的に実態を把握・対応する体制を整備します。人事部門と管理職の連携がカギとなります。
✅ まとめ|実態を知ることが支援の第一歩
「ビジネスケアラーサポート 従業員の介護実態把握ができていない」状態は、多くの企業に共通する課題です。実態を知らなければ、支援策は的外れとなり、離職リスクも防げません。アンケート・相談窓口・管理職教育など多面的なアプローチを通じて、“見えない課題”を見える化し、企業全体で支援に取り組みましょう。
従業員の介護実態を把握についての相談は↓↓↓
<参考>仕事と介護の両立実態把握&サポートサービス