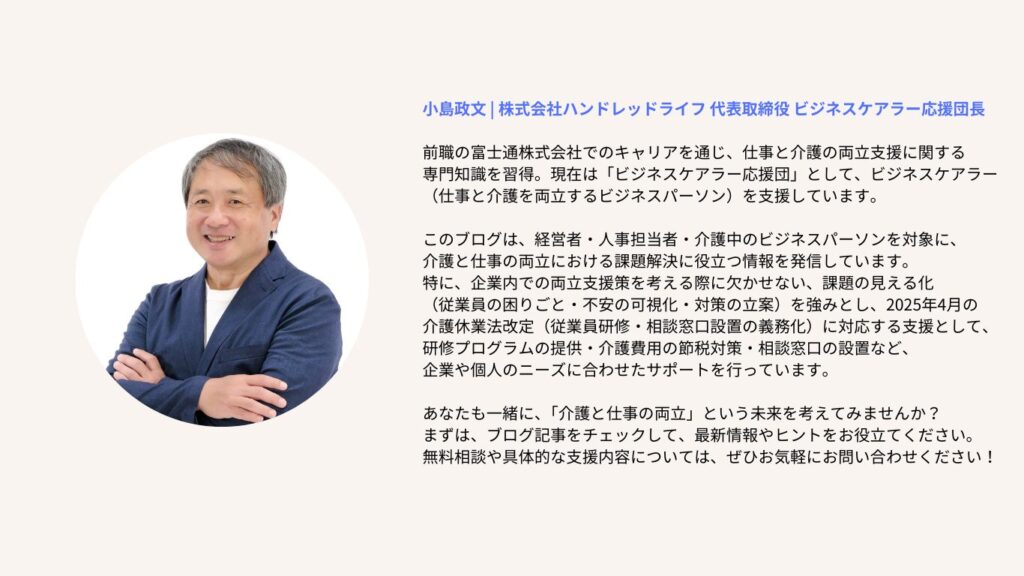「仕事と介護を両立している社員がどれくらいいるのか、正確には把握できていない」「制度は用意したが、実際にビジネスケアラー支援として機能しているか不安」そんな声が、今、多くの企業から聞かれます。介護と仕事を両立する「ビジネスケアラー」は増え続けているにもかかわらず、実態把握が十分に行われていない企業はまだ多数あります。その結果、介護離職やパフォーマンス低下、メンタル不調など、見えないリスクがじわじわと進行しているケースも少なくありません。一方で、限られた人事リソースや予算の中で、すべてを社内だけで対応しようとするのは現実的ではありません。そこで鍵になるのが、「ビジネスケアラー支援×実態把握×外部支援の活用」という考え方です。
この記事では、
- なぜまず「実態把握」が必要なのか
- ビジネスケアラー支援に外部支援者を活用するメリット
- 中小企業でも今日から始められる実践ステップ
までを、5つの視点からわかりやすく解説します。
目次
1. なぜ今、実態把握から始めるビジネスケアラー支援が重要なのか
1-1 制度だけ整えても「ビジネスケアラー支援」になっていない現状
育児・介護休業法への対応が進む中でも、
- 介護をしている社員が何人いるのか
- 「予備軍(今後数年以内に介護が始まりそうな層)」がどれくらいいるのか
- どんな不安や困りごとを抱えているのか
といったビジネスケアラーの実態把握ができている企業はまだ多くありません。
制度や規程だけ整えても、
「そもそも社員が制度を知らない」
「現場の管理職がどう支援してよいか分からない」
という状態では、介護離職防止にはつながりません。だからこそ、ビジネスケアラー支援の出発点は「実態把握」です。

1-2 人的資本経営の観点でも、ビジネスケアラー支援が欠かせない理由
人的資本の情報開示が求められる中で、
- 従業員のライフイベント(介護・育児など)のリスク
- 仕事と介護の両立支援策の有無
- 介護離職・長期離脱の抑制
といった項目は、人的資本経営・ESGの文脈でも重要なテーマになっています。
ビジネスケアラー支援は、
- 離職防止
- エンゲージメント向上
- 採用力・企業イメージの向上
にも直結する「戦略的人事」の領域です。
その前提として、どんなビジネスケアラーが、どのような悩みを抱えているのかを、定量・定性の両面から把握する必要があります。
2. 実態把握から始めるビジネスケアラー支援の進め方
2-1 匿名アンケートで「ビジネスケアラーの見える化」を行う
最初に取り組みやすいのが、匿名アンケートによる実態把握です。
たとえば、こんな項目を盛り込みます。
- 介護・看護を担っている家族がいるか
- その家族が親か、配偶者か、義理の親か など
- 介護にかけている時間(平日/休日)
- 現在感じている不安(時間・お金・メンタル・職場理解など)
- 会社にあったら嬉しいビジネスケアラー支援(制度・情報・相談窓口・研修 など)
ポイントは、
- 「介護をしているかどうか」だけでなく「予備軍」も把握すること
- 記名式ではなく、安心して本音を書ける設計にすること
このアンケートが、ビジネスケアラー支援の土台データになります。
2-2 データ分析で「優先すべき支援テーマ」を絞り込む
アンケート結果は、「集めて終わり」にせず、分析して“打ち手”に変えることが重要です。
たとえば、
- 年代別・部署別にビジネスケアラーの割合を確認
- 「時間の不安」が強いのか、「お金の不安」が強いのかを分類
- 介護経験者と予備軍でニーズの違いを整理
などを行うことで、
「まずは情報提供と相談窓口づくりを優先しよう」
「管理職向けのビジネスケアラー支援研修が必要だ」
「介護費用や制度に関するセミナーが喜ばれそうだ」
といった具体的な優先課題が見えてきます。
この「実態に基づいた優先順位づけ」が、ムダ打ちをしないビジネスケアラー支援の第一歩です。
3. 外部支援を活用してビジネスケアラー支援を強化するメリット
3-1 外部専門家に頼むとできること
「ビジネスケアラー支援の重要性はわかっているが、社内だけでは手が回らない」という企業は少なくありません。そこで有効なのが、外部支援者・専門家の活用です。外部パートナーに依頼できることの一例は、次のとおりです。
- ビジネスケアラー実態把握のためのアンケート設計・集計支援
- 結果分析と「自社向け課題レポート」の作成
- 仕事と介護の両立支援に関する社員研修・管理職研修の実施
- 介護・お金(介護費用・税・社会保障など)に関するセミナー
- 社内相談窓口の立ち上げに関するアドバイス など
ビジネスケアラー支援に特化した外部支援者を活用することで、「何から手を付ければよいか分からない」状態から一気に前進できます。
3-2 中小企業こそ「外部パートナー」を味方につけるべき理由
中小企業では、
- 人事部の人数が限られている
- 制度設計や情報収集を担当する人が兼務になりがち
- 介護や社会保障の専門知識を社内に蓄積しにくい
という現実があります。ここで無理に「すべて社内で完結させよう」とすると、
- 取り組みが一度きりで終わる
- 担当者が変わるとノウハウがリセットされる
- 介護離職の防止まで到達しない
といった事態になりがちです。外部のビジネスケアラー支援パートナーを活用することで、
- 必要なタイミングで必要な専門性だけを取り入れられる
- 社内には「運用」と「判断」に集中してもらえる
- 継続的に改善していく“伴走体制”を築ける
というメリットがあります。
4. ビジネスケアラー支援体制を定着させる運用のポイント
4-1 実態把握を「一度きり」で終わらせない
ビジネスケアラー支援は、
一度アンケートを取って制度を作ったら終了、ではありません。
- 家族の状況
- 介護のステージ
- 法改正や制度変更
などにより、必要な支援は変化していきます。
そのため、
- 年に1回、もしくは2年に1回程度の定期アンケート
- 面談や1on1の場での「ライフイベントの相談」
- 相談窓口に寄せられた声の定期的な振り返り
などを通じて、継続的な実態把握と見直しを行うことが大切です。
4-2 管理職・現場を巻き込んだビジネスケアラー支援
制度や方針だけでは、ビジネスケアラー支援は機能しません。
現場の管理職の理解と行動が非常に重要です。
- ビジネスケアラーが部下にいる場合の対応方法
- 面談での声の聴き方・注意点
- チーム全体への業務調整・情報共有の仕方
といったテーマを含んだ管理職向け研修は、
外部支援者と連携しながら実施すると効果的です。「制度としてはOKでも、上司が理解してくれない」という状態は、介護離職のリスクを高める大きな要因になります。
ビジネスケアラー支援は、人事・経営だけでなく管理職も含めた“組織全体の取り組み”として設計していきましょう。
5. ビジネスケアラー支援パートナー選びのチェックポイント
5-1 「介護」だけでなく「お金・制度」にも強いか
ビジネスケアラー支援では、
- 介護保険や地域資源などの介護の知識
- 税金・社会保険・扶養・控除などのお金・制度の知識
- 仕事と介護の両立支援(就業規則・働き方)の観点
が複雑に絡み合います。
外部支援者を選ぶ際は、
- 介護だけでなく「介護×お金×働き方」の視点で話ができるか
- ビジネスケアラー支援の実績や具体事例があるか
といった点をチェックしておくと安心です。
5-2 「自社に合わせた伴走」をしてくれるかどうか
ビジネスケアラー支援は、企業規模・業種・社員構成によって最適解が異なります。
パッケージをそのまま導入するのではなく、
- 自社の実態把握結果を踏まえて内容を調整してくれるか
- 導入後のフォローや改善提案まで伴走してくれるか
という観点も重要です。
「一度研修して終わり」ではなく、
「実態把握 → 施策実行 → 振り返り → 改善」までサイクルを一緒に回してくれるか?
ここを満たしているパートナーであれば、
ビジネスケアラー支援を中長期の企業戦略として位置づけやすくなります。
まとめ:ビジネスケアラー支援は「実態把握×外部活用」で加速する
ビジネスケアラー支援を本気で進めるなら、
- まずは社員の実態把握から始める
- 実態に即して、優先度の高い支援策を絞り込む
- 限られた社内リソースは、外部支援と組み合わせて補う
- 制度づくりだけでなく、管理職・現場を巻き込んだ運用を行う
- 定期的な実態把握と外部パートナーとのPDCAでブラッシュアップする
という流れが、もっとも現実的で効果的です。
「社内だけでなんとかしなければ」と抱え込む必要はありません。外部のビジネスケアラー支援パートナーを活用しながら、
- 介護離職を防ぎ
- 従業員が安心して働き続けられ
- 企業の人的資本価値も高めていく
そんなビジネスケアラー支援体制を、ぜひ一歩ずつ整えていきましょう。
ビジネスケアラー実態把握に関するご相談は ↓↓↓