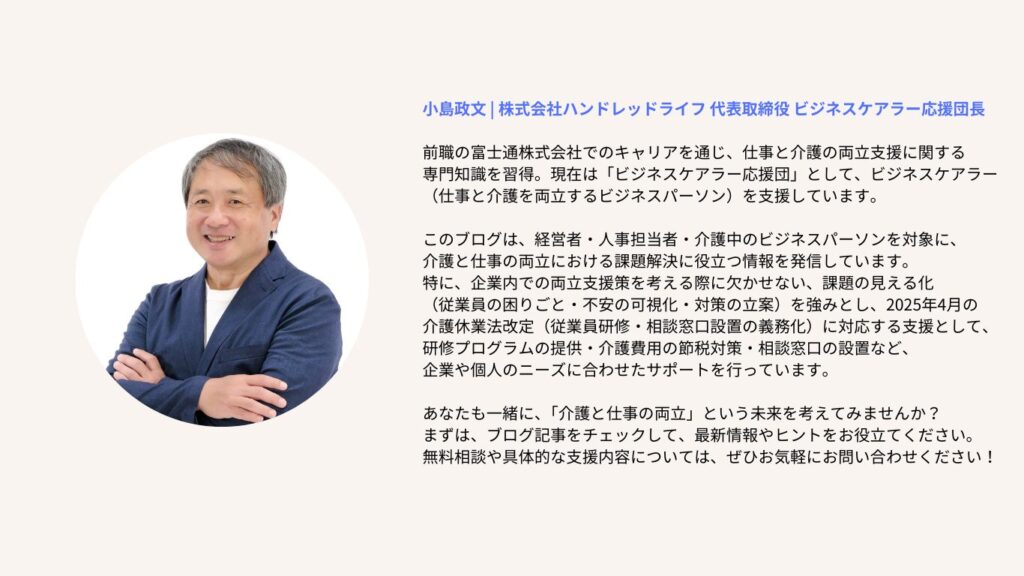働きながら家族の介護を担う「ビジネスケアラー」が増える中、企業には「育児介護休業法」への対応が求められています。特に中小企業にとって、制度対応が後手になることで、人材流出や生産性低下、法的リスクを招くおそれも。本記事では、2025年改正のポイントを押さえつつ、介護を担う従業員への支援体制構築という視点から、「最低限守るべき企業対応」をわかりやすく解説します。
目次
1. 介護に直面する従業員が増える背景とは?
1-1. 働きながら介護を担う人=“ビジネスケアラー”の急増
高齢化が進む日本では、40〜50代の働き盛り世代が親の介護を担うケースが急増しています。「突然の要介護」「施設探し」「ケアマネとの連携」など、精神的・時間的・経済的に大きな負担がのしかかります。

1-2. 企業にとっての“介護リスク”とは?
従業員が介護に直面すると、遅刻・早退・欠勤の増加や離職につながることも多く、企業の生産性・採用コストにも影響します。企業がこのリスクを軽視したまま放置すると、優秀な人材の流出を招きかねません。
2. 育児介護休業法 企業対応|介護休業制度の基本と改正ポイント
2-1. 介護休業と介護休暇の違いを整理しよう
- 介護休業:最大93日間の取得可能。原則3回まで分割も可能。
- 介護休暇:年5日または10日(対象者数により)。半日単位・時間単位で取得可。
それぞれ制度目的・給付金対象も異なるため、企業側がきちんと区別して説明・整備する必要があります。
2-2. 2025年4月改正における企業の新たな義務とは?
- 個別周知・意向確認の義務化
- 制度情報の明示
- 雇用環境整備の義務化(研修・相談窓口・相談体制構築など)
介護を始めた従業員が「制度を知らなかった」「相談しづらかった」と感じる状況を防ぐためにも、制度の“見える化”と周知体制が鍵です。
3. 中小企業が取り組むべき最低限の対応とは?
3-1. 育児介護休業法 企業対応で求められる相談窓口と就業規則の整備
まずは社内に「育児・介護休業制度に関する相談窓口」を設け、従業員が気軽に問い合わせできる環境を整えること。そして、就業規則の中で制度内容を明文化・更新し、常に最新の法改正に即した内容を反映することが重要です。
3-2. 対応が遅れると起きるリスクとは?
- 労働基準監督署からの是正指導
- 従業員からの訴訟・ハラスメント訴え
- 採用広報での企業イメージ低下
制度を設けていても、運用されていない・知られていない状態では意味がなく、企業リスクに直結します。
4. 介護両立支援を促進する制度活用と助成金情報
4-1. 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の活用
厚生労働省の「両立支援助成金」には介護に特化したコースがあり、労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に利用することが出来ます。中小企業にとっては、費用面のハードルを下げる有効な選択肢です。
4-2. 社員研修と管理職への啓発がカギ
制度が形だけで終わらないためには、管理職の理解とマネジメント力の強化が必要不可欠。ビジネスケアラーが相談しやすい環境を作るには、研修や定期的な意識啓発が効果的です。
5. 他社事例に学ぶ「介護支援制度」の実践ポイント
5-1. 柔軟な働き方支援(テレワーク・時短勤務)
介護の段階や状況に応じて、テレワークやフレックス、時短勤務制度を活用できる体制を整えておくことで、離職リスクを大幅に減らすことができます。
5-2. 制度活用チェックリストの配布
「誰が」「いつ」「どのように使えるのか?」を明記した制度活用チェックリストは、従業員の不安解消や制度浸透に役立ちます。社内イントラやメールでの配布、定期的な見直しも推奨されます。
まとめ|中小企業だからこそできる“あたたかい支援”を
「介護が理由で退職せざるを得なかった」——そんな声をなくすためにも、中小企業こそ介護と仕事の両立支援に本気で取り組むべき時代です。育児介護休業法の企業対応は、単なる法令順守ではなく、従業員の人生を支えるエンゲージメント施策そのもの。柔軟な制度整備・助成金の活用・周知啓発の3本柱で、「介護していても働き続けられる会社」を目指しましょう。
ビジネスケアラーサポートに関するご相談は ↓↓↓