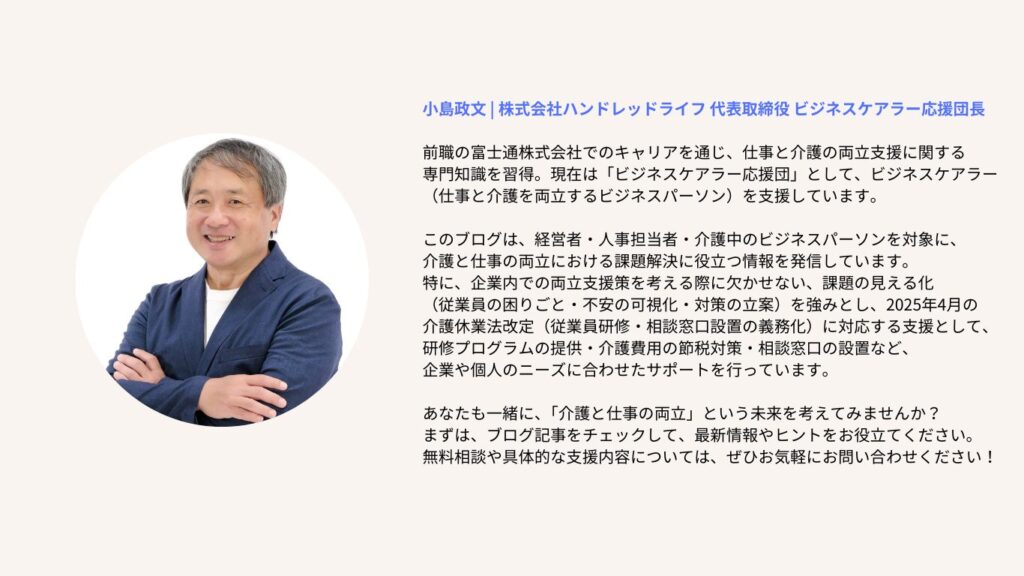「介護のために仕事を休みたいけど、介護休業と介護休暇って何が違うの?」そんな疑問を持つビジネスパーソンが増えています。親や配偶者など家族の介護が必要になったとき、仕事との両立を支える制度として「介護休業」と「介護休暇」が存在しますが、その違いや条件、給付金の有無を正しく理解している方は少ないのが現状です。本記事では、それぞれの制度の違いや介護休業の取得条件・申請方法・給付金制度についてわかりやすく解説。企業に相談する前に知っておきたいポイントをまとめました。
目次
1. 介護休業と介護休暇の違いを整理しよう
1-1 介護休業とは何か?長期間の休業制度
介護休業とは、労働者が家族の介護を理由に最大93日間の休業を取得できる制度です。介護が必要な家族1人につき通算93日まで取得可能で、原則として3回まで分割して取得できます。この間、原則無給ですが、雇用保険の要件を満たすことで介護休業給付金の支給対象となるのが特徴です。

1-2 介護休暇とは何か?短期間の休暇制度
一方、介護休暇は、対象家族1人につき年間5日までの短期的な休暇制度です。これは時間単位・半日単位でも取得可能で、日々の通院付き添いや介護サービスの調整などに利用されます。給与の支給有無は企業の就業規則によって異なり、給付金はありません。
2. 介護休業の取得条件と対象家族
2-1 誰が介護休業を取得できるのか?
介護休業を取得できるのは原則として正社員・契約社員・パートタイム労働者を含むすべての労働者です。ただし、入社6ヶ月未満や、1週間の所定労働日数が2日以下の者など、一部対象外となるケースもあります。雇用契約の期間が満了する予定がある場合なども注意が必要です。
2-2 対象となる「家族」の範囲とは?
介護休業の対象家族は、配偶者(事実婚含む)・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母です。これらの家族に「負傷・疾病・身体障害により2週間以上の常時介護が必要」と医師等に認定された場合、介護休業の対象となります。
3. 介護休業の申請方法と手続きの流れ
3-1 申請タイミングと必要書類
介護休業を取得するには、原則として休業の2週間前までに会社へ書面で申出を行う必要があります。企業によっては申請フォーマットや添付書類(医師の診断書など)を求める場合もあるため、早めに人事担当に確認することが重要です。
3-2 勤務先との調整でトラブルを防ぐ
制度上は労働者の権利として保障されていますが、現場の人員体制や業務の引き継ぎをめぐって摩擦が起きやすいのも現実です。事前に上司と相談し、チームや顧客対応のフォロー体制を整えておくことが、スムーズな取得と職場復帰につながります。
4. 介護休業給付金とは?収入面の不安を軽減
4-1 給付金の支給条件と金額
介護休業中に雇用保険から支給される「介護休業給付金」は、直近6か月の賃金の67%相当額が支給されます。介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していれば介護休業給付を受けることができます。
4-2 給付金の手続きと注意点
申請は基本的に企業が行いますが、書類の提出漏れや不備で支給が遅れるケースもあるため、個人でも内容を確認することが大切です。
5. 介護休業取得時に気をつけたいポイント
5-1 職場復帰後のサポート体制を確認
介護休業が終了した後、スムーズに職場復帰できるかは非常に重要です。職場によっては復帰後の配置変更や役割見直しが発生するため、事前に制度やサポート体制を確認しておくことが望ましいです。
5-2 不利益な扱いを受けないために
法律上、介護休業を理由に解雇・不利益な配置転換などは禁止されています。しかし、現場では「昇進・評価に響くのでは?」という不安の声もあります。万が一、不利益を感じた場合は、労働基準監督署や労働相談窓口への相談も検討しましょう。
まとめ
「介護休業」と「介護休暇」は目的も期間も異なる制度です。特に介護休業は、収入を支える給付金制度がある一方で、取得には条件や調整が必要です。職場との連携や制度理解が、安心して介護と仕事を両立するカギとなります。介護が必要になったら慌てずに、制度の違いや申請方法を正しく知ることから始めましょう。
ビジネスケアラーに関するご相談は ↓↓↓