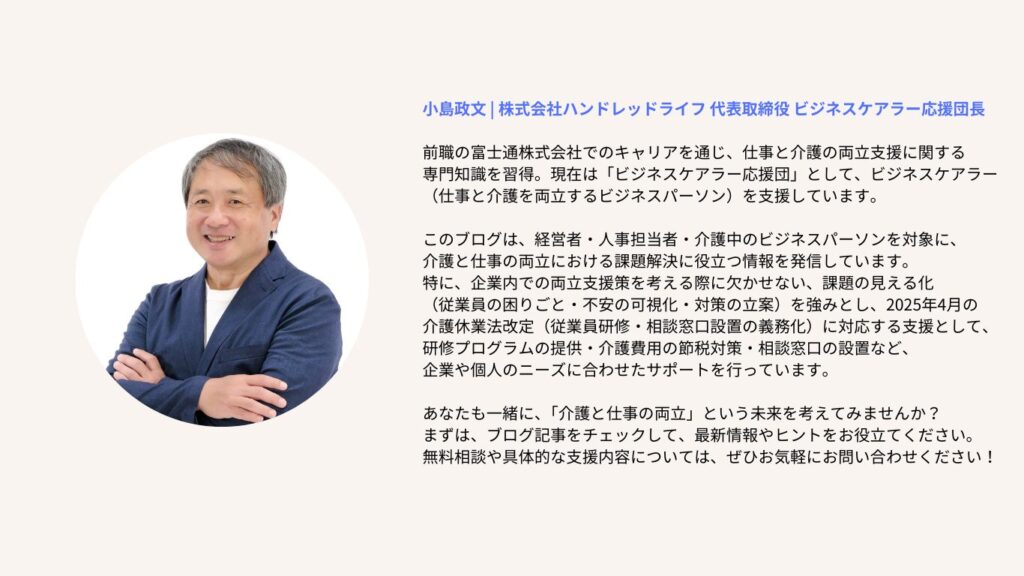介護離職が増え続ける中、従業員の「仕事と介護の両立支援」は企業にとって避けて通れない課題となっています。特に2025年4月から改定された「育児・介護休業法」では、企業に対して介護研修などの実施が義務化され、対応を急ぐ必要があります。本記事では、企業 介護研修の本質的な意義とともに、従業員の介護費用を公的制度で削減する戦略的アプローチをご紹介。制度周知にとどまらず、節税・還付を含む「実益のある研修」へと進化した最新事例をもとに、離職防止と生産性向上を両立するヒントをお届けします。
目次
1. 企業 介護研修の義務化が始まる背景とは
1-1. 高齢化と介護離職の現状
急速な高齢化の進行により、介護を担うビジネスケアラー(働きながら介護を行う人)が年々増加しています。その影響で、企業では「介護を理由に退職・異動する社員」が増え、貴重な人材の損失と生産性の低下が深刻な経営課題となっています。

1-2. 2025年の法改正と企業の義務
2025年4月施行の育児・介護休業法改正により、企業には以下のいずれかが義務化されます:
- 介護リテラシー向上研修の実施
- 相談体制の整備
- 両立支援方針の周知
- 制度利用事例の提供
制度周知だけでは不十分であり、企業 介護研修の実施が今後ますます重要になるのです 。
2. 企業 介護研修が解決すべき3つの課題
2-1. 「制度が複雑でわかりにくい」問題
介護に関わる公的支援制度は、控除、助成、保険と種類が多く、理解も困難です。社員が「知らない」「使えない」状態に陥ると、将来的な離職やメンタル不調のリスクが高まります。
2-2. 経済的不安によるパフォーマンス低下
介護は長期化するケースが多く、介護費用は年間数十万円〜100万円以上になることもあります。金銭的な不安は精神的な重荷となり、業務効率の低下やモチベーション低下を招きます。企業 介護研修では、公的制度や節税知識を伝えることが、この不安の解消につながります。
3. 従業員の介護費用を削減する研修の仕組み
3-1. 公的控除を活用した経済的支援の提供
企業 介護研修では、扶養控除・医療費控除・障害者控除などの公的控除制度の活用方法を具体的に解説。従業員が制度を正しく理解し、年間10万円以上の支出削減が実現できるケースもあります 。
3-2. 専門家による個別診断と還付サポート
研修後には希望者向けに専門家が介入し、家族構成や所得に応じた個別支援・還付サポートを実施することで、実効性を高めます。単なる座学に終わらず、「社員の家計改善につながる研修」として評価される点が特徴です 。
4. 企業 介護研修の導入で得られるメリット
4-1. 離職リスクの低減と生産性向上
介護支援体制が整っている職場では、社員が安心して働き続けることができるため、離職率が下がり、業務への集中力も向上します。また、育成コストや欠員補充コストの削減にも直結します。さらに、介護費用削減につながる知識や制度活用を支援することで、社員の経済的不安を軽減し、離職防止と人的資本の最適化が両立できます。これは企業にとっても「還付金」「扶養控除」などの制度を理解させる実益ある施策です。
4-2. 従業員満足度・企業イメージの向上
介護に関する制度や節税のサポートを研修に組み込むことで、従業員の「介護費用削減」への期待にも応えられます。結果として、福利厚生の質が向上し、「公的控除」や「相談窓口の整備」などを通じて信頼性の高い企業イメージを構築できます。
5. 企業 介護研修を成功させる導入のポイント
5-1. 制度活用に直結する“実用的な内容”にする
法律や制度の基礎だけでなく、具体的な金額効果や活用フローを含む内容でなければ、社員は「自分ごと」として受け止められません。実生活に役立つ内容を盛り込むことが、満足度・定着率を高めるポイントです。
5-2. 管理職・人事部門も巻き込んだ全社的な推進を
管理職や人事部門が介護研修の目的と効果を理解し、現場で活かせるようにしておくことで、研修の成果が組織全体に波及します。また、外部講師や専門家との連携も、中立的な立場からのアドバイスが得られるため有効です。
まとめ
企業 介護研修は、もはや義務への対応にとどまらず、戦略的な人的資本投資の一環として取り組むべきテーマです。特に介護費用の削減につながる研修は、社員と企業の双方に具体的なメリットをもたらします。離職防止、生産性向上、従業員満足度アップ――そのすべての起点となる「実践型の介護研修」を、ぜひ今こそ導入をご検討ください。
企業研修に関するご相談は ↓↓↓
【参考】介護費用の削減と離職防止するプログラム