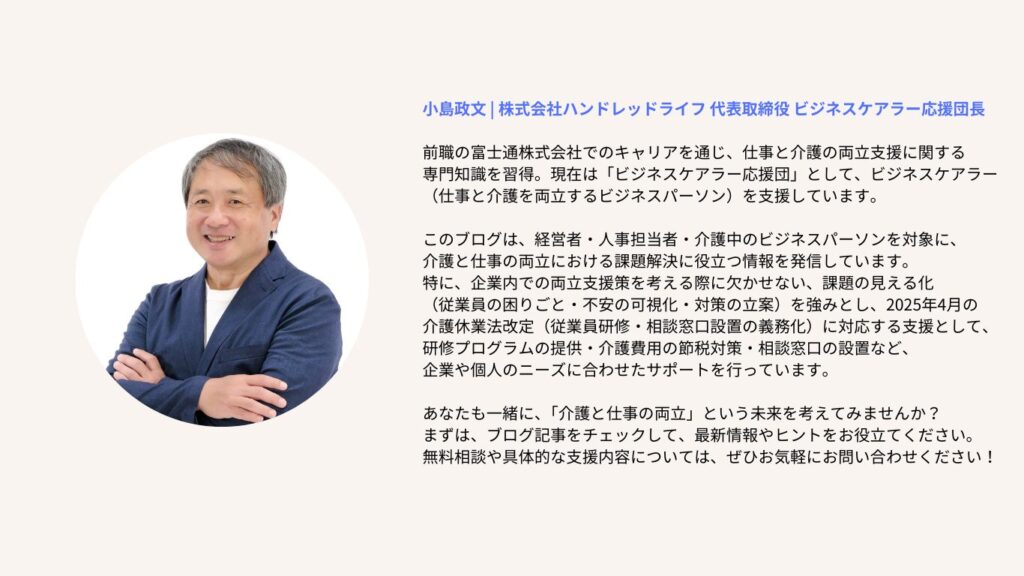介護と仕事を両立する社員“ビジネスケアラー”への支援は、多くの企業にとって急務となっています。特に注目すべきは「介護リテラシー向上」。従業員が正しい情報や知識を持つことは、離職やストレスの予防に直結します。本記事では、ビジネスケアラーサポートにおける介護リテラシー向上の重要性や、その実践方法について、企業が今すぐ取り組める5つの視点から詳しく解説します。

目次
1. なぜ介護リテラシー向上が離職防止につながるのか
1-1 介護リテラシー不足による不安と誤解
介護に直面した際、知識がないことで不安が増し、制度の活用や職場との両立が難しくなるケースがあります。たとえば、ある厚労省の調査では、要介護家族がいる従業員のうち約40%が「制度がよく分からず活用できなかった」と回答。結果として、「介護のためには仕事を辞めるしかない」と誤解して離職を選んでしまうリスクが生じます。
1-2 適切な知識がもたらす職場の安心感
介護に関する正しい情報があることで、相談しやすい雰囲気やサポートを受けやすい職場文化が形成されます。例として、ある企業では介護制度を周知徹底した結果、制度利用者数が3倍に増加。相談件数も増え、離職率も低下しました。
2. ビジネスケアラーサポートが介護リテラシーを高める理由
2-1 仕事と介護の両立支援としての情報提供
ビジネスケアラーサポートの基本は、従業員が介護について学び、理解を深める機会を持つことです。たとえば、「介護保険制度の概要」「地域包括支援センターの活用方法」「要介護認定の手続き」などを丁寧に伝えることで、自身の状況にあった選択肢が見えてきます。
2-2 研修で何が変わる?介護リテラシー定着の具体策
定期的な研修や情報共有会を通じて、介護に関する知識を社員全体で共有することが、企業文化としての“支え合い”を促進します。特に管理職には、部下の相談を受け止める「初動対応マニュアル」や、「介護が始まりそうな兆候の見極めポイント」を含む研修プログラムを導入すると効果的です。
3. 介護リテラシー向上のために企業ができること
3-1 管理職・社員向け研修の導入ポイント
研修では、介護の基礎知識だけでなく、制度利用の流れや実際のケーススタディを取り上げることで理解が深まります。例として、ビジネスケアラー当事者の声を動画で紹介する「ストーリーテリング形式」の研修も効果的です。
3-2 相談しやすい社内環境づくり
介護リテラシー向上を進めるうえでも、相談のしやすさは欠かせない要素です。日常的な声かけのルール化、匿名で相談できるオンラインフォームの設置、またLINE等を活用したチャットボット相談窓口の設置などが有効です。
4. 成果につながるビジネスケアラーサポートの実践法
4-1 制度・ルールを「見える化」する工夫
就業規則や社内ポータルサイトに介護支援制度の内容を明示し、従業員がいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。制度利用のフローチャート、Q&A集、チェックリストを用意し、視覚的にも理解しやすい形にしましょう。人的資本開示の一環として、介護支援制度の明文化と社内公開を進めている企業も増えています
4-2 介護リテラシーを社外と育てる!外部支援活用のすすめ
社内リソースに限界がある場合は、外部の専門のコンサルタントと連携し、個別相談や制度運用の支援を受けることが有効です。月1回の「外部相談日」を設定した企業では、制度利用率が前年比160%に向上した事例もあります。
5. 介護リテラシー向上を定着させる仕組みづくり
5-1 定期的なアンケート・面談でのニーズ把握
介護に関する状況は人によって大きく異なります。従業員の実態を把握するためには、年1〜2回のアンケートやキャリア面談を通じて、定期的に変化をチェックする仕組みが効果的です。アンケートには「家族に介護の必要がある方がいますか?」「制度について十分に理解できていますか?」などの設問を含めましょう。
5-2 従業員と共に育てる支援制度
一方的に制度を整えるのではなく、従業員の声を取り入れながら改善を続けることが、制度の定着と信頼につながります。制度利用後のフィードバックを集め、必要に応じて「改善会議」や「利用者交流会」を開くなど、“使われる制度”をつくる姿勢が重要です。
✅ まとめ
ビジネスケアラーサポートにおける介護リテラシー向上は、単なる制度整備ではなく、企業文化そのものを変える重要な施策です。正しい知識を全社員で共有し、相談しやすい職場を築くことで、離職防止とエンゲージメント向上を両立できます。今こそ、介護への理解を深める第一歩を踏み出しましょう。
📩 介護リテラシー研修・相談窓口の導入支援をご希望の方は、以下よりお気軽にご相談ください。
<参考>ビジネスケアラーサポート研修