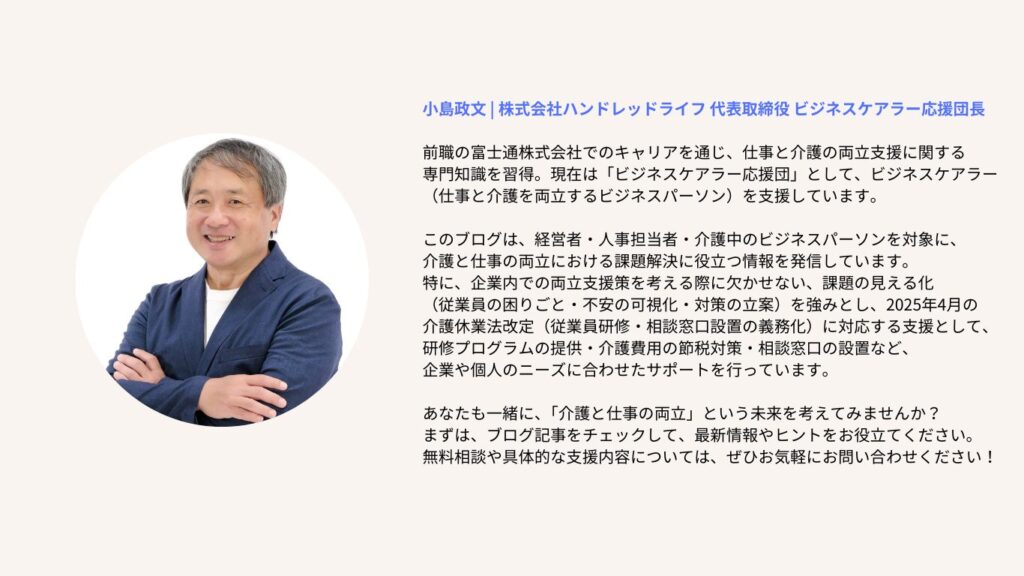近年、企業における育児支援は着実に整備・評価されてきましたが、「企業における育児支援よりも介護の両立支援の取り組みが遅れている」という現状が浮き彫りになっています。介護は突発的で長期化しやすく、支援制度の整備や運用も複雑になりがちです。本記事では、なぜ介護支援が育児支援に比べて評価されにくいのか、その背景や課題を明らかにしつつ、企業が今後取るべき「ビジネスケアラーサポート」の具体策について詳しく解説します。
目次
1. 育児と介護、企業支援の評価に差があるのはなぜか?
1-1 育児支援の社会的認知と制度整備の進展
育児は少子化対策の文脈で国の支援も厚く、法整備や企業導入が先行しています。一方で介護は、属人的で個別対応が求められるため、制度としての標準化や評価が進みにくい傾向があります。
1-2 ビジネスケアラーサポートが育児支援に比べ評価されにくい要因
ビジネスケアラーサポートが育児支援に比べて評価されにくいのは、主に「支援の必要性が見えにくい」ことが原因です。介護の実態が社内で把握されておらず、対象者が申告しづらい雰囲気も課題です。また、制度利用者の声や効果が十分に社内に伝わっていないため、評価が定着しにくい傾向があります。まずは実態の可視化と成果の共有が、介護支援の認知向上に欠かせません。

2. なぜ介護支援は後回しにされるのか?
2-1 介護支援の「見えにくさ」と企業の無関心
ビジネスケアラーは自己申告しにくく、介護の状況は多様なため、企業が実態を把握しづらい傾向があります。このため「支援の必要性」が社内で認識されにくい状況にあります。実際に、ある中堅メーカーでは、介護をしている社員が「制度があっても周囲に知られたくない」という理由で申告できなかったという声もありました。
2-2 制度整備が進まない企業の共通課題
「ビジネスケアラーサポート 育児よりも介護の両立支援での評価が低水準」である企業の多くは、就業規則の未整備・管理職の無理解・相談窓口の不在といった課題を抱えています。また、介護休業法や両立支援等助成金といった制度があっても、社内の就業規則に反映されていない企業が多いのも現実です。
3. 支援が評価される育児制度に学ぶべきポイント
3-1 フレームワークとガイドラインの整備
育児制度では、時短勤務や在宅勤務の基準が明確にされており、利用しやすい環境が整っています。介護支援でも、こうした仕組みの「見える化」が重要です。介護支援制度のガイドライン整備は、ビジネスケアラーが安心して制度を利用するための土台とも言えます。
3-2 情報発信と利用促進の仕掛け
育児支援は企業内で積極的に広報されており、制度利用者の声も紹介されることが多いです。「ビジネスケアラーサポート 育児よりも介護の両立支援での評価が低水準」である現状を打開するには、介護制度の魅力や事例を発信する取り組みが求められます。
4. 介護支援の評価を高めるための実践策
4-1 社内実態調査とビジネスケアラーの可視化
ビジネスケアラー支援を強化するには、まず企業側がどの部署にビジネスケアラーがいるかを把握することが第一歩です。まずは従業員の介護状況を把握するためのアンケートやヒアリングを実施し、「誰が支援対象なのか」を明確にすることが第一歩です。
4-2 制度の見直しと人的資本情報としての開示
ビジネスケアラーサポートは、ESGや人的資本経営の観点からも注目されています。制度内容や利用実績を開示・評価することで、企業価値向上にもつながります。人的資本経営の観点から、従業員のエンゲージメントや介護負担の実態を社内ヒアリングで把握することも、見直しに有効です。
5. 今後の介護支援のあり方と企業の責任
5-1 管理職・人事部門の意識改革
介護支援の評価を高めるには、制度よりもまず現場の理解が不可欠です。管理職に対する「気づき」の教育や、人事部門の運用スキル向上がカギとなります。
5-2 他社事例から学ぶ成功のヒント
「ビジネスケアラーサポート 育児よりも介護の両立支援での評価が低水準」だった企業が成功した背景には、トップダウンの支援推進や従業員の声を反映した制度設計など、具体的な実践がありました。
✅ まとめ|今こそ介護支援を「育児並」に評価される存在へ
育児支援に比べて、介護支援は制度設計・認知・活用のすべての面で遅れを取っているのが現状です。しかし、「ビジネスケアラーサポート 育児よりも介護の両立支援での評価が低水準」という状況を打破するには、まず企業が本気で実態把握・制度整備・社内周知に取り組むことが必要です。今こそ、企業の姿勢が問われています。
介護支援でお困りの方は↓↓↓