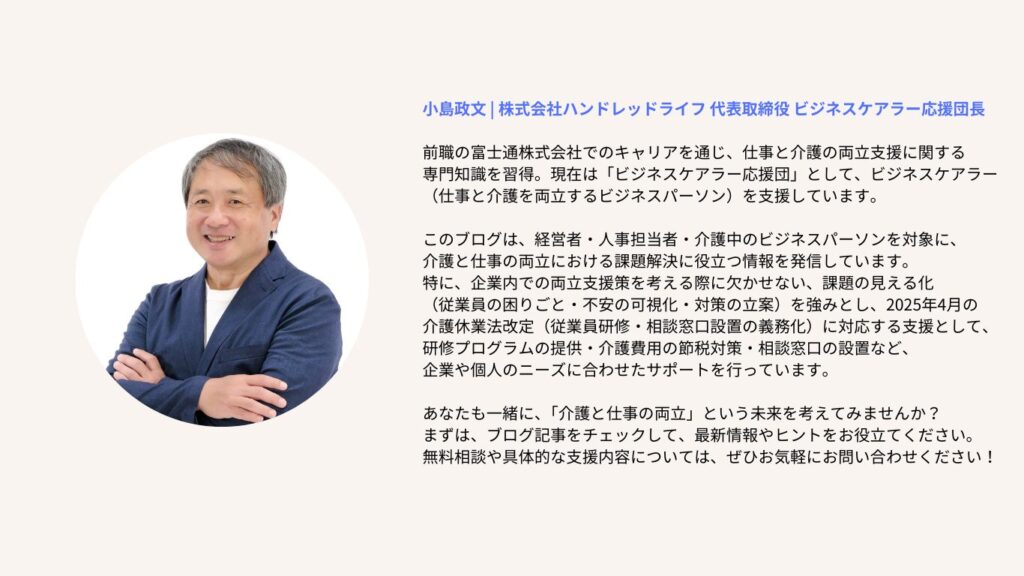人的資本経営が注目を集める中で、従業員の「介護リスク」対策は欠かせないテーマになっています。
仕事と介護を両立する「ビジネスケアラー」の増加に対応するには、企業としてのビジネスケアラーサポート体制強化と、従業員の介護リテラシー向上が不可欠です。
特に2025年の育児・介護休業法改正により、企業には具体的な支援施策が求められる時代へ。本記事では、人的資本経営を強化するために押さえておきたい「ビジネスケアラーサポート」と「介護リテラシー向上」の実践方法について、わかりやすく解説します。
目次
1. なぜ今「ビジネスケアラーサポート」と「介護リテラシー向上」が必要なのか
1-1 ビジネスケアラー増加と人的資本への影響
働き盛り世代(40〜60代)の介護負担が急増し、企業の人的資本に深刻な影響を及ぼしています。
離職、プレゼンティーズム(出社しても集中できない)、生産性低下といった課題は、介護リテラシーの低さも一因。ビジネスケアラーサポート体制がなければ、企業競争力の低下を招くリスクが高まります。

1-2 法改正で義務化される介護リテラシー向上対策
2025年施行の改正育児・介護休業法では、「介護リテラシー向上研修」や「相談窓口設置」が企業義務に。
単なる制度周知ではなく、介護リテラシー向上によって従業員が自ら支援を活用できる状態にすることが求められます。
2. ビジネスケアラーサポート導入の基本ステップ
2-1 社内実態調査で介護リスクを見える化
まずはビジネスケアラーサポート設計の第一歩として、従業員アンケートやヒアリングを実施。「介護中」「今後リスクあり」といった状況を把握することで、実態に即した介護リテラシー向上施策が計画できるようになります。
2-2 ビジネスケアラーサポート成功に向けた経営層コミットメントの重要性
人的資本経営の一環として、経営層がビジネスケアラーサポートに本気で取り組むことを宣言するのが重要。
社内外に発信することで、介護リテラシー向上の取り組みに説得力が生まれ、社員の安心感も高まります。
3. 介護リテラシー向上に効果的な施策とは?
3-1 介護リテラシー向上研修の設計と実施ポイント
ビジネスケアラーのための研修は、「介護保険制度」「費用負担」「相談先情報」など、実用的な知識に特化することがポイント。
さらに、上司向けの「部下支援スキル研修」も介護リテラシー向上に不可欠です。
3-2 社内相談窓口・外部支援サービスの活用
ビジネスケアラーサポート強化には、専門相談窓口の設置が有効。
また、社内だけで限界を感じる場合は、外部の介護相談サービスや賢約サポートのような支援も組み合わせ、介護リテラシー向上と利用促進を両輪で進めます。
4. ビジネスケアラー支援の効果を可視化する
4-1 KPI設定で介護リテラシー向上を数値化
効果測定には、「介護リテラシー研修受講率」「介護相談件数」「制度利用率」などのKPI設定は、介護リテラシー向上の取り組み効果を「見える化」するために不可欠です。これにより、ビジネスケアラーサポート施策がどれだけ機能しているかを見える化できます。
4-2 人的資本レポートやIR資料への反映
成果は「人的資本経営レポート」や「IR資料」にも反映。介護離職防止の観点や人的資本開示との整合性を持たせながら、ESG指標としても支援施策を明示することが、投資家や求職者の評価向上に直結し、ブランディングにもつながります。
5. 未来に向けたビジネスケアラーサポート戦略
5-1 ビジネスケアラーサポートによるエンゲージメント向上施策へ
単なる離職防止にとどまらず、ビジネスケアラーサポートを「従業員エンゲージメント向上施策」として位置付けることで、企業全体の活性化につなげます。
5-2 外部パートナーとの連携による介護リテラシー向上の加速策
自社単独では難しい部分は、外部パートナーとの協働でDEI(多様性・包括性)を意識した介護リテラシー向上策を進めることが重要です。人的資本開示対応にも有効で、ESGの観点からも注目されています。
まとめ
ビジネスケアラーサポートと介護リテラシー向上は、単なる福利厚生ではありません。人的資本を守り育てるための「経営戦略」であり、これからの企業成長の土台となります。2025年改正法施行されたことを契機に、今こそ本気でビジネスケアラー支援に取り組むタイミングです。従業員の未来、そして企業の未来を守るため、最初の一歩を踏み出しましょう。
<参考>ビジネスケアラーサポート研修