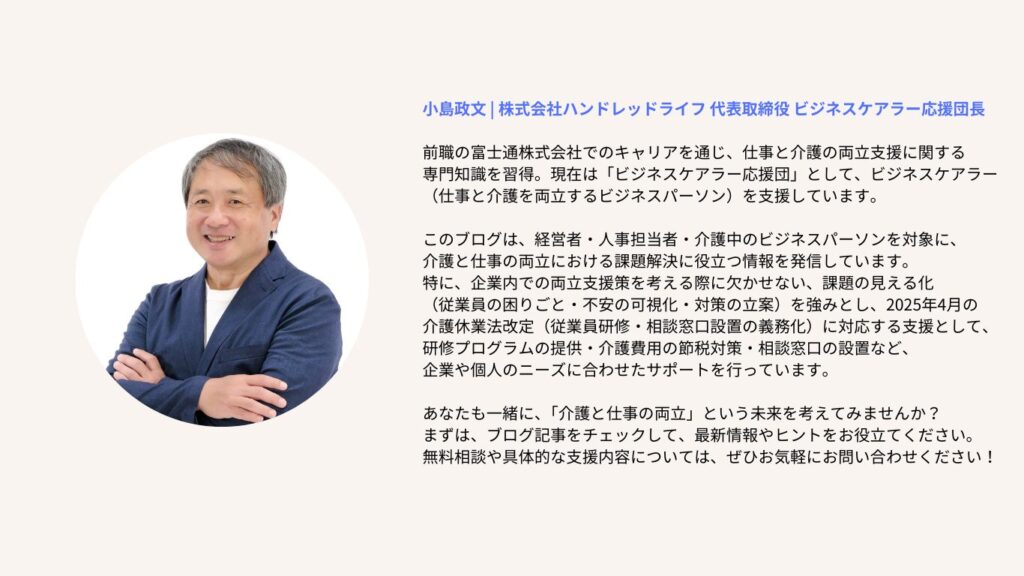高齢化の加速と介護人材不足が深刻化する日本社会において、企業の中核を担う40〜60代が家族介護を抱える「ビジネスケアラー」の増加は、もはや避けられない現実です。介護と仕事の両立に悩む従業員が増えることで、企業は介護離職、生産性低下、人材流出といった経営リスクに直面しています。
本記事では、「なぜ今ビジネスケアラー支援が企業にとって不可欠なのか」をデータと事例から解説。経済損失9.1兆円という衝撃的な予測をもとに、人的資本経営・ESG・健康経営の視点から、企業が取るべき支援策とその効果をわかりやすくご紹介します。
「何から始めればいいかわからない」という企業こそ、“見える化”から始めてみませんか?
目次
1. 深刻化する「介護人材不足」と家族へのしわ寄せ
1-1 介護職員21万人不足、深刻な採用難
総務省人口推計によると2024年10月1日現在で、65歳以上の高齢者が約3624万人に達しました。特に75歳以上の増加が著しく、介護需要は今後さらに拡大します。しかし、厚生労働省の推計によると22年度の職員数は25万人で介護人材は40年度に57万人不足すると見込まれています。

1-2 介護を担うのは「家庭」、特に現役世代
介護人材不足により介護サービスが利用できない・不十分な場合、介護の担い手は家族です。特に40〜60代の就業者、いわゆる「ビジネスケアラー」が負担の中心に。介護離職や業務効率の低下といった影響が、企業や社会全体に及ぶリスクは無視できません。
2. 増え続けるビジネスケアラーと経済的損失の拡大
2-1 ビジネスケアラーは2030年に318万人へ
経済産業省の予測によると、働きながら介護するビジネスケアラーは2030年には318万人に増加。2020年比で56万人の増加が見込まれており、介護と仕事の両立支援は今や「個人の問題」ではなく、国家的な課題です。
2-2 年間9.1兆円の経済損失を生む介護離職
同省の試算では、介護による離職やプレゼンティーズム(出社していても集中できない状態)によって、経済的損失は2030年に年間9.1兆円にも上るとされています。これは日本の生産性をさらに低下させる要因のひとつです。
3. 企業の人的資本経営に「ビジネスケアラー支援」が不可欠
3-1 ビジネスケアラー支援による離職防止・生産性維持
介護と仕事を両立できる環境を整えることは、離職を防ぎ、優秀な人材の流出を防ぐだけでなく、社員のロイヤルティやエンゲージメント向上にもつながります。
3-2 制度整備だけでは不十分!使いやすい職場づくりがビジネスケアラー支援のカギ
介護休業や時短勤務などの制度整備に加え、「使いやすい」職場の雰囲気づくりが重要です。介護離職防止の観点からも、上司の理解やチーム内での情報共有、DEI(多様性・公正・包括性)を意識した組織文化の醸成があってこそ、ビジネスケアラー支援は真に機能します。
4. 行政と企業の連携がカギを握る時代へ
4-1 東京都・千葉県などの介護人材確保策
各自治体も対応を急いでいます。東京都では介護職員への処遇改善策や、資格者の再就職支援を実施。千葉県では外国人材の育成・定着支援を通じ、すでに100人以上が就職しています。
4-2 企業が主導する「両立支援」の拡大が求められる
自治体任せではなく、企業が独自にビジネスケアラー支援の体制を整えることで、人材確保・競争力強化にもつながります。人的資本経営や人的資本開示の観点からも、ビジネスケアラーの実態把握と支援は企業価値の可視化に直結します。ESG・DEIといった非財務情報との連携も、今後重要性を増すでしょう。
まとめ:介護と仕事の両立支援は、経済成長を守る“社会的投資”
超高齢社会のなかで急増するビジネスケアラーの課題は、もはや個人や家庭だけで抱える問題ではありません。企業にとっても、人的資本の損失、生産性の低下、採用難といった経営上の大きなリスクに直結しています。一方で、戦略的な「ビジネスケアラー支援」は、人的資本経営・ESG・健康経営といった複数の経営テーマとリンクし、人的資本開示や介護離職防止といった要素も含めて、企業価値の向上やリスクマネジメントにもつながります。
今こそ、仕事と介護の両立支援を「コスト」ではなく「成長投資」として捉え、持続可能な組織づくりを始める絶好のタイミングです。
📣 あなたの会社も“見える化”から始めてみませんか?
ハンドレッドライフでは、ビジネスケアラー支援の第一歩として
✅ 従業員の実態把握アンケート
✅ 公的支援・税制の活用アドバイス
✅ 介護リテラシー向上研修
✅ 社内向け相談窓口の整備支援
など、企業の状況に合わせたカスタマイズ支援をご提供しています。
👉 「何から始めればよいかわからない」方へ、まずは無料相談から
ご相談は以下のボタンよりお気軽にご連絡ください。