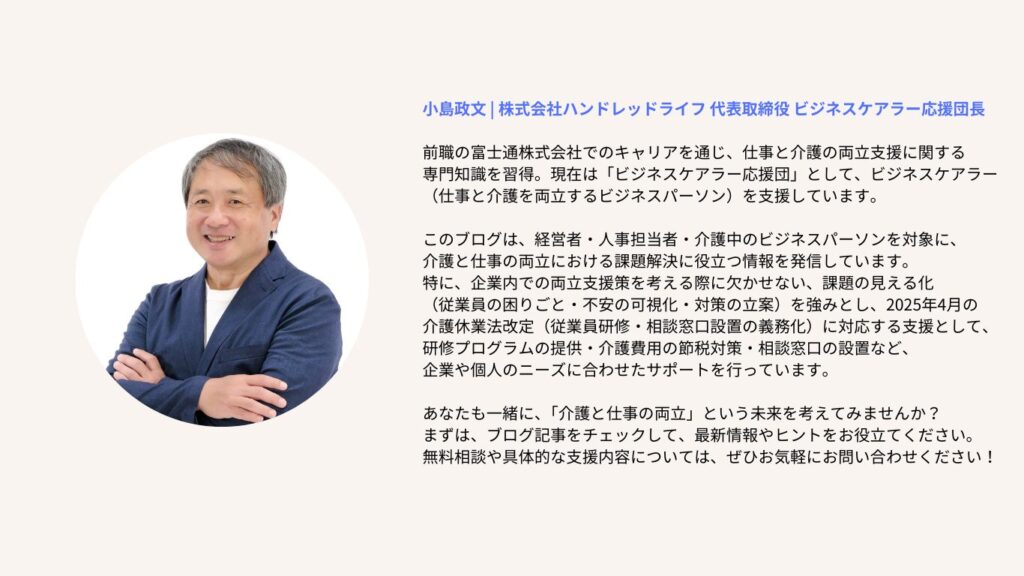日本の急速な高齢化に伴い、「介護と仕事を両立する従業員=ビジネスケアラー」が増加しています。企業にとっては離職リスクや生産性の低下といった課題に直結するため、放置できない問題です。2025年4月には育児・介護休業法の改正も施行され、企業にはより積極的な対応が求められています。今注目されているのが、人的資本経営の一環としての「ビジネスケアラー支援」です。本記事では、人的資本経営を実現し、離職防止・生産性向上・企業価値向上を同時に叶えるための支援制度や導入ステップについて解説します。
目次
1. なぜ「ビジネスケアラー支援」が経営に必要なのか?
1-1 日本の高齢化と企業のリスク
日本は急速な高齢社会を迎えており、総務省の統計によると2030年には約4人に1人が65歳以上の高齢者となる見込みです。これに伴い、要介護者の数も増加の一途をたどっており、その介護の担い手として「現役世代」が前面に立たされる構図が浮き彫りになっています。
特に、企業の中核を担う40〜50代の管理職層が家族介護に直面するケースが増えています。こうした「働きながら介護を担う従業員=ビジネスケアラー」が増加することで、業務への集中が難しくなったり、最悪の場合は介護離職を選択せざるを得なくなったりする事態も起こります。
これは企業にとって、人材の喪失・組織力の低下・生産性の減退といった、経営リスクそのものであり、放置できない経営課題となっています。

1-2 放置できない経済的損失
経済産業省の調査では、「仕事と介護の両立支援」がなされないことによる経済的損失は、年間9.1兆円にものぼると試算されています。これは、企業が採用・教育・引き継ぎにかけるコストが大幅に増えることや、出社していても集中できない“プレゼンティーズム”の増加、組織全体の士気低下などが主な要因です。
また、中小企業1社あたりでも年間平均773万円の損失が出る可能性があるというデータもあり、決して大企業だけの問題ではありません。
このような損失を防ぐには、今から「ビジネスケアラー支援」に着手することが重要です。次章では、企業が「介護と仕事の両立支援」を通じて得られるメリットを詳しく見ていきます。
2. ビジネスケアラー支援は「人的資本経営」につながる
2-1 支援制度の導入で可視化される「従業員価値」
人的資本経営の中核は、「従業員をコストではなく資産として捉える」ことです。介護支援制度を導入することで、従業員一人ひとりの健康・安心感・エンゲージメントが可視化され、結果として組織全体の生産性や定着率が向上します。
たとえば、介護の負担が軽減されることで、集中して業務に取り組める環境が整い、パフォーマンスの最大化につながるのです。
2-2 ESG・健康経営との相乗効果
「ビジネスケアラー支援」は、ESG投資における「S(社会)」の要素や「健康経営」との相性も非常に高い取り組みです。従業員のワークライフバランスを尊重し、実際にサポート体制を整えている企業は、投資家や求職者からの信頼も得やすくなります。
人的資本経営の実践において、介護支援の整備は単なる福利厚生ではなく、企業価値を高める戦略的施策として、今後ますます注目される分野となるでしょう。
3. 今すぐ始めるべき!企業が取り組むべき具体策
3-1 介護リテラシー向上研修の実施
まずは従業員向けに介護保険制度や支援制度の基礎知識を周知することが重要です。特に、管理職には部下の介護事情に気づく力や配慮の仕方を伝える「両立マネジメント研修」が効果的です。
3-2 実態の把握と相談体制の整備
アンケートやヒアリングを通じて、社内にどれだけビジネスケアラーがいるかを可視化し、社内に相談窓口を設けましょう。専門家と連携した1on1対応も、早期介入・離職防止に効果的です。
4. 柔軟な働き方と制度の導入が支援の鍵
4-1 働き方の柔軟化:時間・場所・役割の調整
在宅勤務、時短勤務、スライド勤務などを導入することで、介護と両立しやすい環境が整います。また、育児と異なり「予測しにくい」のが介護の特徴なので、柔軟性の高い制度が重要です。
4-2 制度だけでなく「風土」も整える
制度があっても使えない雰囲気があると意味がありません。経営層や上司の理解と発信、成功事例の共有が「使いやすさ」を後押しします。
5. ビジネスケアラー支援を成功させる外部連携のすすめ
5-1 専門機関との連携で、効果的な制度運用へ
外部の専門家と連携することで、制度設計から研修、個別対応までを一貫してサポート可能になります。自社だけで対応しきれない実務的・心理的サポートをカバーできます。
5-2 ハンドレッドライフのサポート例
たとえば、ハンドレッドライフでは以下のような支援を提供しています:
・介護費用削減セミナー・相談窓口の設置支援
・介護リテラシー向上研修(制度活用・節税対策)
・人的資本経営に直結する改善提案と実行支援
まとめ:人的資本経営に、介護支援は不可欠な時代へ
「仕事と介護の両立支援」は、単なる福利厚生ではなく、企業の持続的成長に不可欠な投資です。
ビジネスケアラー支援を人的資本経営に戦略的に組み込むことで、離職防止・組織の安定・企業価値向上という“三方良し”の成果が得られます。
無料相談はこちら
<参考>介護離職を防ぐ企業研修